ホーム > 方代の年譜
ここから本文です。
更新日:2022年5月16日
方代の年譜
甲州 右左口村
旧右左口村は、甲府盆地の南部に位置し、現在の甲府市右左口町に属する。生家のあった宿地区を通る右左口路は甲斐の古道の1つ。 一般に、中道往還と呼ばれ、甲斐と駿河を結んでいた。迦葉坂、女坂(阿難坂)は御坂山地を越えて、精進・本栖へ至る峠道の名である。右左口村は、1924(大正12)年の時点で戸数580戸、人口4078人。養蚕が盛んになり、収入の7割を収めたのもこの頃である。
方代誕生
山崎方代は、1914(大正3)年11月1日、父龍吉(65歳)、母けさの(45歳)の二男として誕生。八人兄弟の末っ子であった。「方代」という名は、長女くま、五女ひでこ以外の子どもを亡くした両親が「生き放題、死に放題」にちなんで名付けたという。
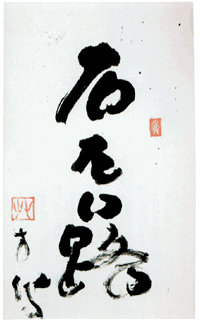
「右左口路」幅
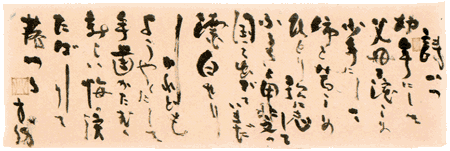
「詩一つ」額装
右左口青年団と「ふたば」
右左口の青年集団の古くは、若居者衆と呼ばれ、祭礼などに強い発言力を持っていた。明治40年頃、青年矯正会に改編。大正5年、右左口青年団となった。「ふたば」は右左口青年団文芸部・雄弁部発行の雑誌である。1935(昭和10)年7月発行第九巻第一号の巻頭言は、山崎方代が執筆。論説、散文、詩、短歌、俳句などを66ページにわたり掲載している。方代は山崎一輪名で詩や短歌を発表した。
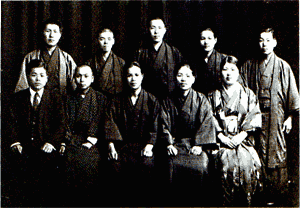
右左口地上歌会集合写真(昭和8.9年頃)
前列左より2人目が山崎方代
横浜へ
1937(昭和12)年11月25日に母けさのが亡くなる。方代は翌年の2月、神奈川県横浜市の歯科医に嫁いでいた姉、関くまのもとへ父とともに移り住む。方代、歌への志を胸に、右左口を発つ。

関くま(1895~1965)
横浜浅間町時代の方代を物心両面で支えた。
兵士として
方代は、1941(昭和16)年7月、陸軍東部第77部隊に入隊。昭和17年7月野戦高射砲第33大隊の一等兵として宇品港より出帆、シンガポール、ジャワ島、チモール島と転戦。昭和18年と19年の二度にわたり、チモール島クーパンの戦闘で負傷。1946(昭和21)年6月、帰還。負傷によって右眼は失明、左眼も視力0.01となっていた。

軍隊時代の方代肖像写真
日本を発つ直前、陸軍東部第77部隊で一緒だった山梨出身の大窪政男氏に贈ったもの。
「一路」から「工人」へ
方代は、1947(昭和22)年「一路」1月号掲載の短歌3首から復帰。筆名は、本名のみ使うようになる。1948(昭和23)年10月、山形義雄、長倉智恵雄、芝山永治、岡部桂一郎らとともに「一路」を離れ、「工人」を創刊。この頃方代はしばしば帰郷し、「工人」山梨市部歌会などに参加していた。
泥の会
泥の会、1949(昭和24)年、宮柊二が呼び掛けて開いた集まりをきっかけとして始まった。メンバーは岡部桂一郎、金子一秋、葛原繁、三木アヤら。翌年、伊藤麟、片山貞美、草柳繁一、杉本二木雄、深作光貞、森比佐志、山崎方代らが加わる。会は約10年間の活動を経て、同人誌「泥」を発行する。「泥」は1958(昭和33)年11月から1964年まで、10号が出された。方代はほぼ毎号に短歌を寄せた。
『方代』と『山崎方代歌集』
「方代』に収録された作品は全部で200首、「工人」「黄」に発表された作品と、書き下ろしと思われる歌を含む。それぞれの歌に番号がつけられている。方代が残した草稿類の中に『山崎方代歌集』とい表紙がつけられた草稿がある。この草稿の98首の短歌と『方代』収録作品とを照合してみると55首が一致しており、『方代』との関連が考えられる。「工人」「黄」などには発表されていないものも多く。『方代』の成立を考える上で興味深い資料である。
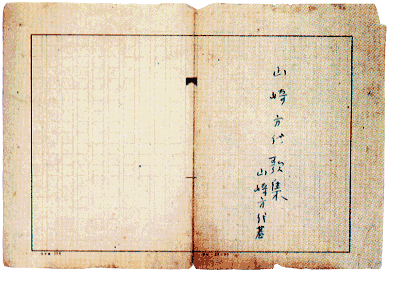
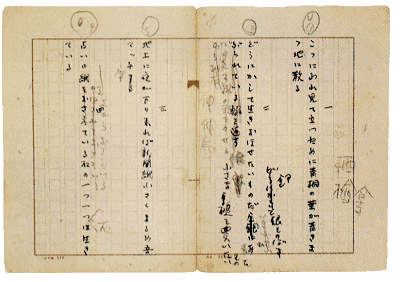
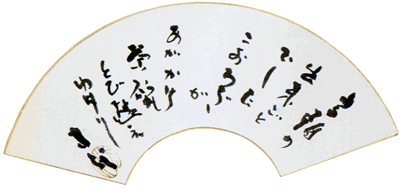
ある朝の出来事でしたこおろぎがあがかけ茶碗とび越えゆけり
色紙「こおろぎ」所収
1969(昭和45)56歳
11月26日、右左口町の七覚山円楽寺に山崎家一族の墓を建立。

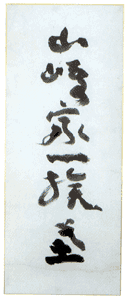
1972(昭和47)58歳
- 7月、鎌倉八幡宮前にある鎌倉飯店の店主、根岸侊雄氏が鎌倉市手広の自宅に6畳1間の家を建て、方代を迎える。
- 9月、左眼白内障悪化。国立相模原病院に入院。手術。視力0.01に戻り、退院。
1985(昭和60)71歳
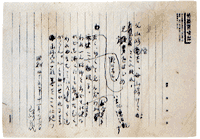
- 1月11日、藤沢市民病院に入院する。
- 3月18日、同病院にて肺ガン摘出の手術を行う。入院中、戸塚の国立病院に放射線治療のため通院する。
- 8月6日、国立横浜病院に入院。
- 19日、肺癌による心不全のため死去。
- 20日、鎌倉瑞泉寺にて通夜。
- 21日、同寺にて葬儀。
- 31日、円楽寺にて本葬。
- 10月、「短歌」「追悼・山崎方代」「新宴」40号「追悼山崎方代」
- 11月、「海山」追悼山崎方代
- 12月、「短歌現代」山崎方代追悼



