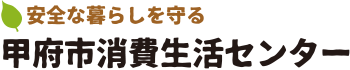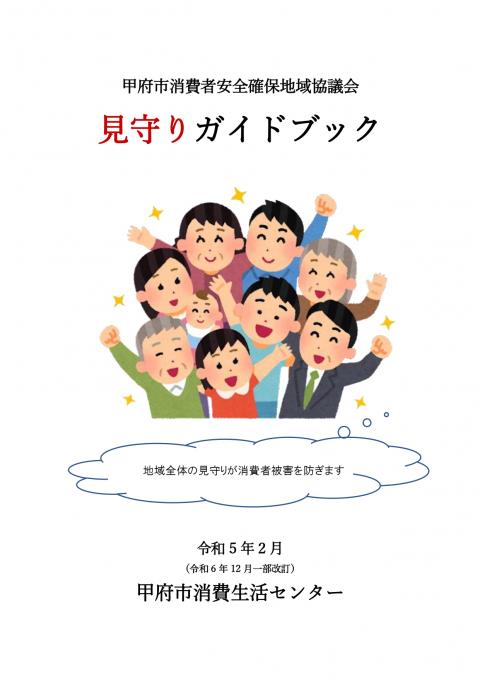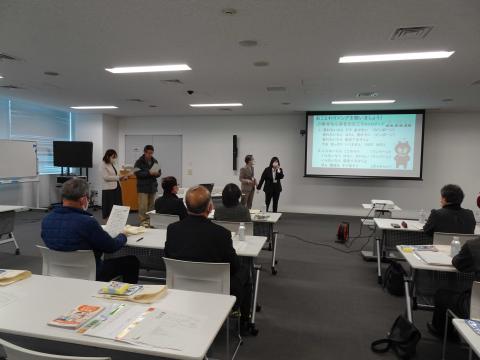- 甲府市消費生活センター
- 055-237-5309
- 甲府市ホームページ
ホーム > 地域で見守り
ここから本文です。
更新日:2024年12月19日
地域で見守り
近年、一人もしくは夫婦だけで暮らす高齢者世帯が増えています。それに伴い、高齢者を狙った消費者トラブルが後を絶ちません。消費生活センターには、高齢者を狙った消費者トラブルの被害相談が増えています。
高齢者の消費者被害を防ぐために、今、地域の皆さんの力が求められています。
見守り活動は、決して難しいことではありません。
まず大切なことは、普段の暮らしの中で高齢者との交流をはかり、関係を密にしておくことです。家族や近所に住む皆さん、ヘルパーさんなど福祉関係の人など、高齢者に接する機会の多い人が日ごろから高齢者の様子を気にかけることが、高齢者を消費者被害から守ることにつながります。
高齢者見守り活動の流れ
身近な高齢者と日ごろからコミュニケーションをはかり、関係を密にしておくことで、高齢者のささいな変化に気付くことができます。また、信頼関係があれば、声をかけたときに高齢者もより相談しやすくなります。
- 声かけ:高齢者に、声をかけましょう。
- 事実確認:何があったのか、事実を確認しましょう。
- つなぐ:消費者被害にあっていたら、消費生活センターへの相談を勧めましょう。
気づきのポイント
一緒に暮らしていて…
- 家族が知らない荷物が届いた
- 見慣れない商品がある
- 開けていない段ボール箱がある
- 宅配便や郵便物が頻繁に届くようになった
- 入金を督促する請求書が届いている 等
家を訪ねたときに…
- 来客がよくある(販売員や宅配業者など)
- 同じような商品が必要以上にある
- たくさんのダイレクトメールや請求書などの郵便物が届いている
- 不自然なリフォーム工事がしてある 等
会話をしているときに…
- 急に親しい人ができたようだ
- 投資などに急に関心を持ち始めた
- 羽振りのいい話が多くなった
- 霊感・祈祷などに関心を持ち始めた
- 特定の話題に急に詳しくなった 等
地域で見かけたときに…
- 見慣れない人がよく出入りしている
- 外出が急に増えたようだ
- 見知らぬ人に話しかけられていた
高齢者の消費者トラブルの特徴
孤独を狙われる
高齢者は、日ごろのコミュニケーション不足から、寂しさを抱えている人が多いです。特に一人暮らしの場合は、普段の話し相手がいない分、優しい言葉で語りかけてくれる販売員のことを「親切な人だ」と感じ、家に招き入れてしまう傾向があります。
高齢者の「ほこり」が相談をはばむ
人に迷惑をかけないことを美徳とする高齢者は多いものです。たとえ被害にあったとしても、「だまされた自分が悪いんだ」と自らを責め、ほかの人に迷惑がかからないよう、誰にも相談せずにいたり、家族に知られたくないと隠すケースが目立ちます。
お金の不安につけこまれる
老後を安心して暮らしたいと願う高齢者にとって、老後のお金の問題は大きな不安要素です。収入に不安がある高齢者は、販売員の「必ず儲かる」といううたい文句を信じ、金融商品などの契約をしてしまいます。
健康への不安を利用される
多くの高齢者は、何かしらの身体の不調を感じています。悪質業者はそうした高齢者が抱える健康不安につけこみ、「痛みが治る」「血圧が下がる」などといううたい文句で、高額な商品を購入させようとします。
「あれ?」と思ったら
声かけをとおして被害にあっていることが確認できた場合には、気軽に消費生活センターへの相談を勧めましょう。電話はもちろん、窓口での相談もできます。窓口を訪問するときは、家族や支援者が付き添うこともできます。
- 消費者安全確保地域協議会
消費者安全の確保のための取組を効果的かつ円滑に行うために必要な情報交換を行い、取組みに関する協議を行うため、平成28年11月に消費者安全確保地域協議会を設置し、見守りネットワークの構築を図ってきました。
協議会の構成員は、協議会における協議の結果に基づき、消費者安全の確保のため、消費生活上特に配慮を要する消費者と適当な接触を保ち、その状況を見守ること、その他の必要な取組みを実施していただいています。
事業者等に向けた消費者見守りマニュアル
見守りネットワークの更なる充実に向け、地域の事業者等に向けた「消費者見守りマニュアル」を作成しました。
本マニュアルは、地域に密着した事業者等の皆様が、業務中に「あれ?何かおかしいな?」「普段と様子が違うな」などと、「高齢者等の異変(消費者被害の兆候)」に気づかれた際の対応方法をまとめたものです。
高齢者等消費者の見守りは、何か特別なことをしていただく必要はありません。業務中に高齢者等の何らかの「異変」に気づいた際は、本人にさりげなく声かけをしていただき、困っているようであれば、消費生活センターや地域包括支援センターなどの相談機関があることをお伝えいただき、相談を勧めていただくなど、さりげない見守りをお願いします。
また、本市では、消費者被害の防止や消費者の見守りに関する出前講座も行っておりますので、ご希望がありましたらお問い合わせ先までご連絡をお願いします。
「事業者等に向けた消費者見守りマニュアル」(PDF:617KB)
- 消費者見守りサポーター養成講座
「消費者見守りサポーター」とは、高齢者等の消費者被害を地域で見守り、関係機関につなぐ役割をしていただくサポーターのことです。消費者に関する様々な知識や見守りのノウハウを身につけていただき、消費者被害を防ぐことを目的とした講座です。
地域の方々の見守りが、消費者被害を防ぐことにつながりますので、高齢者等の変化に「気づき」、「声かけ」を行い、消費生活センターや関係機関に「つなぐ」お手伝いをしてみませんか?
過去の講座では、山梨大学の神山久美教授(安全確保地域協議会会長)や、警察、弁護士、全国消費生活相談員協会の方々を講師に迎え、消費者被害の防止等について、様々な視点から講演を行っていただきました。
今後も様々な講師をお迎えして、消費者被害の防止について講座を行いますので、ぜひご参加ください。