ホーム > 市政情報 > 広報 > わくわくキッズ > まずは甲府の今を見てみよう > 甲府の産業
ここから本文です。
甲府の産業
研磨宝飾(けんまほうしょく)
甲府市は、地場産業として宝石加工がさかんなところです。
甲府市では、宝石(ダイヤ、サファイヤ、エメラルドなど)や貴金属(金やプラチナなど)を使って、指輪・ネックレス・イヤリングなどのアクセサリーや、置物・茶器のように家にかざるものなどがたくさん作られ、日本全国で売られています。
むかしは、甲府市の北部でとれた水晶を使っていましたが、今は世界中から仕入れた水晶や、人工水晶を使っています。また、今は水晶・宝石・貴金属をつかった新しい品物の開発や、ほかの地域の伝統産業と組み合わせた新しい製品の開発も行っています。
全国に先がけて「県立宝石美術専門学校」もつくられました。それに、技能検定にちょうせんしたり、「技能オリンピック」にも参加したりして、技術の向上もはかっています。
甲州印伝(こうしゅういんでん)
印伝(いんでん)の名前の由来は印度伝来(いんどでんらい)によるといわれています。
鹿(しか)の革を松の脂でいぶし、うるしでもようを染め出したもので、うるしは時がたつほど色がさえ、深みのある落ち着いた光沢になってきます。うるしもようづけされた柔らかく丈夫で軽い鹿皮の袋物は、使い込むほど手に馴染み、愛着が増します。
印伝の特徴の一つである鹿革は、体になじみ強度があるため、かつては武士のすね当てやよろい兜(かぶと)にも使われました。明治時代になると、信玄袋や巾着袋などが内国勧業博覧会で表彰されるなど、甲州印伝は、山梨の特産品として確固たる地位を築きました。その後、袋物だけでなく流行をふまえて、大正時代にはハンドバックなどさまざまな製品がつくられました。
江戸時代には各地で製造されたと思われていますが、現在、製法が伝わっているのは、甲州印伝のみです。
農業・林業
甲府市では、自然を生かして多くの作物が作られています。
どこで、どんな作物がさかんに作られているのか、地図で確認してみましょう。
甲府の特産物
ぶどう

日当たりのよい山ぎわのけいしゃ地や、水はけのよい平地で行われるぶどう作りは、甲府市の地形や気候に合っていて、昔からさかんです。そのため、ぶどうは江戸時代から特産品となり、1695年「本朝食艦」という本では、ぶどうの産地として甲州が第1位とされています。明治時代には甲州種のほかにも、西洋種を取り入れたり、ワイン醸造(じょうぞう)も行われたりするようになり、さらに生産量を伸ばしました。現在では、収穫したぶどうの多くは、日本全国に送られています。
とうもろこし

中道地区では昭和41年から、とうもろこしの栽培が始まりました。
「昼夜の温度差が大きい」という盆地特有の気候と、「日照時間が長い」・「笛吹川が育んだ肥沃(ひよく)な土壌がある」などの良い条件を活かし、今では山梨県一の生産量を誇っています。
ワイン
日本でワインが作られるようになったのは明治3年です。「文明開化はワインから」を合言葉に、甲府の有志によって始められました。明治3・4年ごろ、甲府の広庭町(現在の武田2・3丁目)で行ったぶどう酒の醸造が国産ワインの始まりで、ワインは甲府が発祥の地といわれています。
現在、甲州ワインは生産量・味とも国産ワインのトップクラスになっています。
山梨県内には、約80のワイナリー(ワインを生産するところ)があります。多くのワイナリーでは、ワインの製造過程の説明を受けられたり、試飲ができたりするなど、ワインを楽しむことができます。
湯村温泉

湯村温泉は、1200年前に弘法大師(こうぼうだいし)が開湯したといわれています。信玄公のかくし湯としてしられ、葛飾北斎(かつしかほくさい)の「勝景奇覧(しょうけいきらん)甲州湯村」に描かれたことでも有名です。
また、昭和の大作家である太宰治(だざいおさむ)や井伏鱒二(いぶせますじ)、松本清張(まつもとせいちょう)らが留まり、本を書いた宿もあります。
今でも毎分1トンにもなる良質の高温泉がわき出て、たくさんの観光客が訪れています。
|
★甲府の昔へタイムスリップ! |

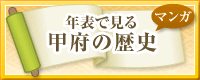
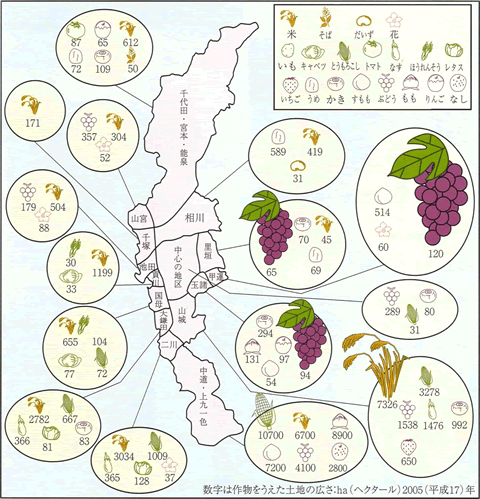 (PNG:1,840KB)
(PNG:1,840KB)