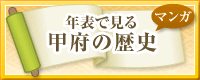ここから本文です。
寺社・史跡
善光寺

善光寺は、武田信玄によって1558年(永禄元年)に建てられた浄土宗(じょうどしゅう)の寺です。
戦国時代、信州にあった善光寺が戦火によって焼けてしまうことを恐れた信玄が、仏像や寺の宝物を甲府に移して開きました。本堂は木造建築で、東日本で最大級の規模を誇り、山門や阿弥陀三尊像(あみださんぞんぞう)とともに国の重要文化財です。
甲府五山
武田信玄は、府中(※1)やその周辺の5つの寺院のことを、府中五山(甲府五山)と定めました。信玄は仏教を信仰し、多くの寺院・僧侶をうやまって保護しました。なかでも禅法をとうとび、その教えを政治にも取り入れ、厚く保護しました。
※1府中:政治の中心地のこと
長禅寺(ちょうぜんじ)

信玄の母の大井夫人の菩提寺(ぼだいじ)です。寺には大井夫人のお墓があります。信玄の弟の逍遥軒信綱(しょうようけん のぶつな)が、亡き母の供養のために描いた「大井夫人画像」が国の重要文化財に指定されています。
東光寺(とうこうじ)

鎌倉にある建長寺(けんちょうじ)を建てた蘭渓道隆(らんけい どうりゅう)によって、密教(みっきょう)から臨済宗(りんざいしゅう)に改められた寺です。
寺には、信玄に捕らえられ、この寺で自ら命を絶った諏訪頼重(すわ よりしげ)の墓と、父である信玄とのいさかいから寺に閉じこめられ、自害した息子の武田義信の墓があります。
中でも庭園は見事で、後世の日本の庭園文化に強い影響を与えています。
また仏殿(薬師堂)は、室町中期の唐様(からよう)建築物として国の重要文化財になっています。
円光院(えんこういん)

信玄の正室である三条夫人の菩提寺(ぼだいじ)です。円光院の名前は、夫人が亡くなった後、その法号をとって付けられました。寺には、信玄の寄進状(きしんじょう)や遺宝(いほう)が残されています。
法泉寺(ほうせんじ)

信玄の息子の勝頼の菩提寺(ぼだいじ)です。
勝頼は、1582年(天正10年)に、織田信長に敗れ、その首は京にさらされましたが、この寺の和尚(おしょう)が、その歯と髪の一部をもらいうけ、境内に埋葬(まいそう)したと伝えられています。
能成寺(のうじょうじ)

信玄の高祖父(※1)である、武田信守が建てた臨済宗(りんざいしゅう)の寺です。
芭蕉(ばしょう)の俳句が彫られた石碑(せきひ)もあります。
※1高祖父:おじいさんのおじいさん
舞鶴城

舞鶴城は、甲府城の別名で、白壁が重なり合う優雅な姿から「鶴が羽根を広げたような城」という意味で呼ばれました。この城は、武田氏が滅びた後、豊臣秀吉の命令で、関東の徳川家康に対抗するための重要な拠点として築かれました。その後、江戸時代には、江戸の西を守る城として、とても重要な役割を果たしました。
明治時代になると、甲府城は城として使われなくなり、明治10年前後には、主な建物はほとんど取り壊されました。
1964年(昭和39年)には都市公園「舞鶴城公園」となりました。
平成2年から、舞鶴城公園整備事業として復元が行われました。
|
★甲府の昔へタイムスリップ! |
藤村記念館

昭和42年に国の重要文化財となった藤村記念館は、昭和44年から郷土の民俗・歴史・教育・考古資料の展示館として長く親しまれてきました。
平成22年10月に甲府駅北口に移転し、現在では交流ガイダンス施設として利用されています。
寺社・史跡MAP
このページで紹介した寺社・史跡がどこにあるのか地図で確認してみよう!
より大きな地図で 甲府市の寺社・史跡 を表示
|
★甲府の昔へタイムスリップ! |