ホーム > 教育・文化・スポーツ > 文化 > 文化財 > 武田史跡
更新日:2021年6月15日
ここから本文です。
武田史跡
武田神社

武田神社は大正8年(1919)に躑躅が崎館跡(武田氏館跡)に創建され、甲斐の名将・武田信玄がまつられています。
永正16年(1519)、信玄の父・信虎が躑躅が崎館をつくり、信虎・信玄・勝頼の3代が63年間にわたって住んでいました。現在では、この館跡は国の史跡に指定されています。
信玄の詠歌といわれている「人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり」との歌でわかるとおり、信玄には城も石垣もいらず、小さな館で十分であったと思われます。
神社社殿の東側には宝物殿があり、武具や軍配、軍旗など武田氏ゆかりの品々が納められています。
見所
宝物殿(要拝観料)
住所
甲府市古府中町2611
電話
055-252-2609
甲斐善光寺

武田信玄によって永禄元年(1558)に創建された浄土宗の寺です。戦国時代、信州善光寺が戦火によって焼失することを恐れた信玄が、仏像・寺宝を甲府に移し、自らが開基となったことに始まります。本堂は木造建築で、東日本で最大級の規模を誇り、山門や阿弥陀三尊像とともに重要文化財です。
見所
重要文化財
「銅造阿弥陀三尊像」
「木造阿弥陀三尊像」
宝物館(本堂・宝物館とも要拝観料)
住所
甲府市善光寺3-36-1
電話
055-233-7570
積翠寺と要害城跡(せきすいじ・ようがいじょうあと)

臨済宗妙心寺派行基が創建し、その後、夢窓国師弟子竺峰和尚が一時衰えた寺を興し、武田家の菩提所として再建しました。この寺は、境内の巨石から泉が涌き出ていたことで、石水寺と呼ばれていましたが、いつごろからか積翠寺に改められています。
大永元年(1521)11月3日、戦火を逃れて要害城に避難した信虎夫人は、この寺で信玄を出産したと伝えられています。現在も産湯を汲んだ井戸があり、産湯天神が祭られています。
寺院裏には釣鐘をふせたような山(要害山)が見えますが永正17年(1520)、躑躅が崎の援護地として信虎が築城した要害城跡です。
見所
市文化財「武田信玄和漢連句」
産湯天神
住所
甲府市上積翠寺町984
電話
055-252-6158
信玄墓

信玄の墓はこのほか、山梨県内では大泉寺、恵林寺、長野県の諏訪湖、長岳寺と竜雲寺、和歌山県高野山、愛知県福田寺、京都の妙心寺など全国にあります。
これは信玄が遺言によって、喪を3年間秘めていたことや万一の外敵を恐れて、埋葬地を秘密にしていた結果とも見られています。
見所
県文化財(天然記念物)
「八房梅」
住所
甲府市岩窪町北部幼児教育センターの前
大泉寺(だいせんじ)
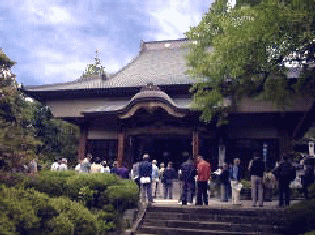
大永元年(1521)、武田信虎が天桂禅長を開山として建てた寺で、信虎の菩提寺です。
天正2年(1574)3月、信虎が信州で没した時、その遺骸を国元に送り、ここに埋葬されました。
この寺も戦災のため、法堂、庫裡などを焼失しましたが、幸い、武田3代の霊廟、総門、宝蔵は火をまぬがれ、霊廟には信虎・信玄・勝頼3代の肖像が安置されています。
見所
信虎・信玄・勝頼の墓
重要文化財
「絹本著色武田信虎像」(信玄の弟である、逍遥軒信綱画)
「絹本墨画松梅図」
住所
甲府市古府中町5015
電話
055-253-2518
入明寺(にゅうみょうじ)

62代村上天皇の苗裔六条有成が得度、浄閑と称し長享元年(1487)、創建された寺です。
この寺には信玄の次男・武田信親(竜宝・竜芳)の墓があります。信親の子・信道の子孫が連綿と続き、現在は武田家17代英信氏です。
見所
武田信親の墓
住所
甲府市住吉4-13-36
電話
055-228-2907
甲府五山
武田信玄公は広く仏教を信仰し、宗旨のいかんを問わず、寺院・僧侶を崇敬保護しました。
なかでも信玄は禅法を尊び、臨済禅の関山派に深く帰依し、京都や鎌倉五山にならって、府中とその周辺に府中五山(甲府五山)を定めました。
よくある質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

