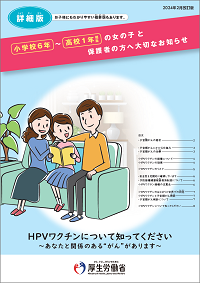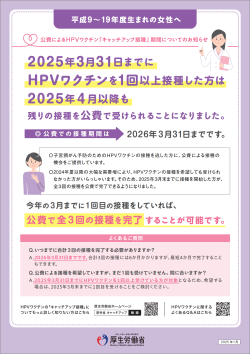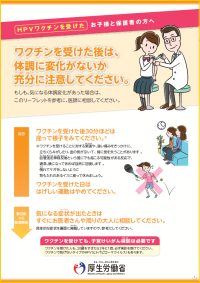更新日:2026年1月28日
ここから本文です。
HPVワクチン(子宮頸がんワクチン)の接種について
ヒトパピローマウイルス(HPV)は、性的接触のある女性であれば50%以上が生涯で一度は感染するとされている一般的なウイルスです。子宮頸がんをはじめ、肛門がん、膣がんなどのがんや、尖圭コンジローマ等、多くの病気の発生に関わっています。特に、近年若い女性の子宮頸がん罹患が増えています。
HPV感染症を防ぐワクチン(HPVワクチン)は、小学校6年~高校1年相当の女子を対象に、定期接種を行っています。
令和8年度からのHPVワクチン(子宮頸がんワクチン)について
令和8年度からサーバリックス®(2価ワクチン)とガーダシル®(4価ワクチン)は定期予防接種で用いるワクチンからは除くこととなり、シルガード®(9価ワクチン)のみになります。
接種対象者
(1)定期接種対象年齢の方
| 小学6年生(12歳)相当 | 平成25年4月2日生まれ〜平成26年4月1日生まれ | |
| 中学1年生(13歳)相当 | 平成24年4月2日生まれ〜平成25年4月1日生まれ | ☆標準的な接種年齢 |
| 中学2年生(14歳)相当 | 平成23年4月2日生まれ〜平成24年4月1日生まれ | |
| 中学3年生(15歳)相当 | 平成22年4月2日生まれ〜平成23年4月1日生まれ | |
| 高校1年生(16歳)相当 | 平成21年4月2日生まれ〜平成22年4月1日生まれ |
(2)キャッチアップ接種経過措置の対象の方
- キャッチアップ接種対象者のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方
- 平成20年度生まれの女子で、令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方
期間:キャッチアップ接種期間(令和7年3月31日)終了後、1年間
令和6年夏以降の大幅な需要増により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃる状況等を踏まえ、令和7年3月末までに接種を開始した方が、全3回の接種を公費で完了できるようになりました。
最新の情報については厚生労働省のホームページ(別サイトへリンク)をご確認ください。
HPVワクチン(子宮頸がんワクチン)の種類と接種間隔
HPVの中には子宮頸がんをおこしやすい種類(型)のものがあり、HPVワクチンは、このうち一部の感染を防ぐことができます。
現在、日本国内で使用できるワクチンは、防ぐことができるHPVの種類によって、2価ワクチン(サーバリックス)、4価ワクチン(ガーダシル)、9価ワクチン(シルガード9)の3種類あります。
サーバリックスおよびガーダシルは、子宮頸がんをおこしやすい種類であるHPV16型と18型の感染を防ぐことができます。そのことにより、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぎます。
シルガード9は、HPV16型と18型に加え、31型、33型、45型、52型、58型の感染も防ぐため、子宮頸がんの原因の80~90%を防ぎます。
サーバリックス®(2価ワクチン)
1回目の接種から1ヶ月の間隔をあけて2回目を接種後、1回目接種から6ヶ月の間隔をおいて3回目を接種
ガーダシル®(4価ワクチン)
1回目の接種から2ヶ月の間隔をあけて2回目を接種後、1回目接種から6ヶ月の間隔をおいて3回目を接種
シルガード®(9価ワクチン)
1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合:1回目接種から6ヶ月の間隔をあけて2回目を接種
1回目の接種を15歳になってから受ける場合:1回目接種から2ヶ月の間隔をあけて2回目を接種後、1回目接種から6ヶ月の間隔をおいて3回目を接種

3種類いずれも、1年以内に接種を終えることが望ましい。
※1 1回目と2回目の接種は、少なくとも5ヶ月以上あけます。5ヶ月未満である場合、3回目の接種が必要になります。
※2・3 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2ヶ月後と6ヶ月後にできない場合、2回目は1回目から1ヶ月以上(※2)、3回目は2回目接種から3ヶ月以上(※3)あけます。
※4・5 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の1ヶ月後と6ヶ月後にできない場合、2回目は1回目から1ヶ月以上(※4)、3回目は1回目から5ヶ月以上、2回目から2ヶ月半以上(※5)あけます。
※「〇か月の間隔をおいて」とは、接種日の〇か月後の同じ日に接種できます。
(例:1月1日に接種し、1か月の間隔をおく→次は2月1日以降に接種をする)
接種場所
子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)接種可能医療機関一覧(PDF:92KB)
リーフレット
(PDF:2,782KB) (PDF:3,667KB) (PDF:103KB) (PDF:1,274KB)
リーフレット(概要版) リーフレット(詳細版) リーフレット(キャッチアップ) リーフレット(受けた後版)
◯関連リンク
HPVワクチン(子宮頸がんワクチン)接種に関する相談窓口
甲府市のHPVワクチン(子宮頸がんワクチン)相談窓口
医務感染症課相談窓口
電話番号:055-237-2587
受付日時:月曜日~金曜日、午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
山梨県のHPVワクチン相談窓口
HPVワクチン接種後に症状が生じた方に対する相談・支援(山梨県)(別サイトへリンク)
県庁健康増進課(医療、救済などに関すること)
電話番号:055-223-1497
受付日時(共通):月曜日~金曜日、午前9時~正午・午後1時~午後5時(祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
県庁保健体育課(教育、学校生活などに関すること)
電話番号:055-223-1785
受付日時(共通):月曜日~金曜日、午前9時~正午・午後1時~午後5時(祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
厚生労働省のHPVワクチン相談窓口
電話番号:0120-995-956
受付日時:月曜日~金曜日、午前9時~午後5時(祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
HPVワクチンの主な副反応
HPVワクチン接種後には、接種部位の痛みや腫れ、赤みなどが起こることがあります。
まれですが、重い症状(重いアレルギー症状・神経系の症状)※1 が起こることがあります。
| 発生頻度 | サーバリックス®(2価) | ガーダシル®(4価) | シルガード®(9価) |
|---|---|---|---|
| 50%以上 | 疼痛、発赤、腫脹、疲労 | 疼痛 | 疼痛 |
| 10〜50%未満 | 掻痒(かゆみ)、腹痛、筋痛、関節痛、頭痛 | 紅斑、腫脹 | 腫脹、紅斑、頭痛 |
| 1〜10%未満 | じんましん、めまい、発熱など | 頭痛、そう痒感、発熱 | 浮動性めまい、悪心、下痢、そう痒感、発熱、疲労、内出血など |
| 1%未満 | 知覚異常、感覚鈍麻、全身の脱力 |
下痢、腹痛、四肢痛、筋骨格硬直、硬結、出血、不快感、倦怠感など |
嘔吐、腹痛、筋肉痛、関節痛、出血、血腫、倦怠感、硬結など |
| 頻度不明 | 四肢痛、失神、リンパ節症など | 失神、嘔吐、関節痛、筋肉痛、疲労など | 感覚鈍麻、失神、四肢痛など |
※1 重いアレルギー症状:呼吸困難・じんましん等(アナフィラキシー)
神経系の症状:手足の力が入りにくい(ギラン・バレー症候群)、頭痛、嘔吐、意識低下(急性散在性脳脊髄炎(ADEM))等
厚生労働省厚生科学審議会(予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会)において、報告を受けた情報を分析し、ワクチンの安全性や有効性を評価しています。
最新の情報・報告数等については、厚生科学審議会 (予防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会)のホームページ(別サイトへリンク)をご確認ください。
各回の資料等▶資料→各種PDF資料(〜ワクチンの副反応疑い報告状況について)
接種後に生じた症状の診療について
気になる症状が起こった場合、接種を行った医療機関を受診してください。
予防接種による健康被害についての補償(救済)に関する相談
予防接種(定期接種・臨時接種)により健康被害が生じた場合、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
詳しくは予防接種健康被害救済制度についてをご確認ください。
厚生労働省の疾病・障害認定審査会における、予防接種による健康被害の認定状況・認定件数等は以下からご確認ください。
疾病・障害認定審査会 (感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)(別サイトへリンク)
各回の資料等▶審議結果→PDF審議結果
平成25年4月1日以降に接種した方(定期接種の方)
定期接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
健康被害救済制度についてをご覧ください
平成25年3月31日以前に接種をした方(任意接種の方)
予防接種法に基づかない接種(任意接種)として取り扱われるので、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA)に基づく救済を受けることができます。
医薬品副作用健康被害救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)(別サイトへリンク)
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
生活衛生室医務感染症課感染症係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-237-2587
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください