令和4年度から実施される個人市民税・県民税(住民税)の主な税制改正内容
更新日:2025年1月16日
ここから本文です。
令和4年度から実施される個人市民税・県民税(住民税)の主な税制改正内容
住宅借入金等特別控除の特例の延長
経済対策として住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例期間が延長されました。次に掲げる要件を満たす場合、控除期間が13年に延長された住宅借入金等特別控除を適用することができます。
適用条件
- 一定の期日※1までに、新築住宅、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等に係る契約を行っていること
- 令和4年12月31日までの間に1.の住宅に入居していること
※1新築住宅の場合:令和3年9月30日まで
建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合:令和3年11月30日まで
※ただし、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である特例居住用家屋の場合、合計所得金額1,000万円以下という所得要件があります。
表(市・県民税における住宅ローン控除)
| 措置 |
住宅ローン控除 (消費税8%への引き揚げ時に反動減対策として拡充した措置) |
消費税10%引き上げに伴う反動減対策の上乗せ措置 |
コロナ特例 ※コロナを踏まえた上乗せ措置の弾力化 |
経済対策として控除期間13年間の措置を延長 |
|---|---|---|---|---|
| 居住開始年月日 | 平成26年4月~令和3年12月 | 令和元年10月~令和2年12月 | 令和3年1月~令和3年12月 | 令和3年1月~令和4年12月 |
| 控除限度額 |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高13.65万円) |
同左 | 同左 | 同左 |
| 控除期間 | 10年 | 13年 | 同左 | 同左 |
| 面積 | 50㎡以上 | 同左 | 同左 |
40㎡以上 ※40㎡以上50㎡未満の場合は合計所得金額1,000万円の所得要件あり |
(市・県民税における住宅ローン控除)(財務省より引用)
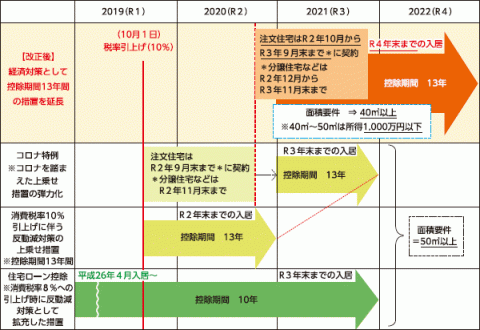
※詳しくは国土交通省ホームページ(別サイトへリンク)をご覧ください。
※住民税における住宅借入金等特別税額控除について(甲府市サイト内ページ)
セルフメディケーション税制の見直し
対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し※2、セルフメディケーション税制の適用期限を5年延長しました。また、「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類の添付または提示は不要になりました。
※2令和4年分(令和5年度)より適用となります。
退職所得課税の適正化
令和4年1月1日以降に支払われるべき退職手当等から、退職所得の算出方法が一部変更となりました。雇用の流動化等に配慮し、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金について、退職所得控除額を除いた300万円までは2分の1課税を適用し、それ以上の部分については全額課税となります。
勤続年数が5年以下の法人役員等以外の場合
(1)退職所得控除を除いた退職手当等の支払金額が300万円以下の場合
(退職手当等の支払金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得
(2)退職所得控除を除いた退職手当等の支払金額が300万円以上の場合
150万円+{退職手当等の支払金額-(300万円+退職所得控除額)}=退職所得
退職所得(財務省より引用)
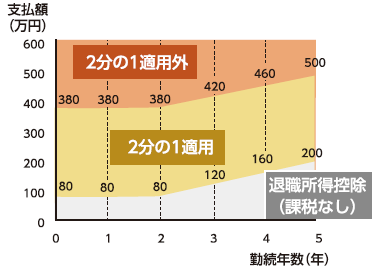
※退職所得に係る個人市・県民税について、詳しくはこちらへ
国や地方公共団体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方公共団体からの子育てに係る助成等については非課税所得となります。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの使用料に対する助成とします。
(例)ベビーシッター等の利用料に係る助成、認可外保育施設等の利用料に係る助成、一時預かり・病児保育等の子を預ける施設の利用料に係る助成
※上記の助成と一体として行われる助成についても対象(例:生活援助・家事支援・保育施設等の副食費・交通費等)
その他改正
ふるさと納税(寄附金控除)の申告手続の簡素化
寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされていますが、令和3年分の確定申告から、特定寄附金の受領者が地方団体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。
手続きの詳しい内容は、国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)を確認してください。
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
市・県民税において、令和3年中の配当所得及び株式等に係る譲渡所得等が、特別徴収されたもののみであり、そのすべてを住民税において特別徴収で済ませること(申告不要)としようとする場合(所得税においてもその全てを申告不要とする場合を除きます。)、原則として確定申告書を提出するのみで手続きが完結できるよう、確定申告書に附記事項が追加されることになりました。申告不要とする場合は、確定申告書第二表の住民税に関する事項における「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇をつけてください。

| 注意 |
|---|
|
「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○をつけた場合、原則として、お住まいの市区町村に対する住民税の申告書の提出は不要となりますが、以下の点にご留意ください。
|
よくある質問
お問い合わせ
税務管理室市民税課個人市民税係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)
電話番号:055-237-5398
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

